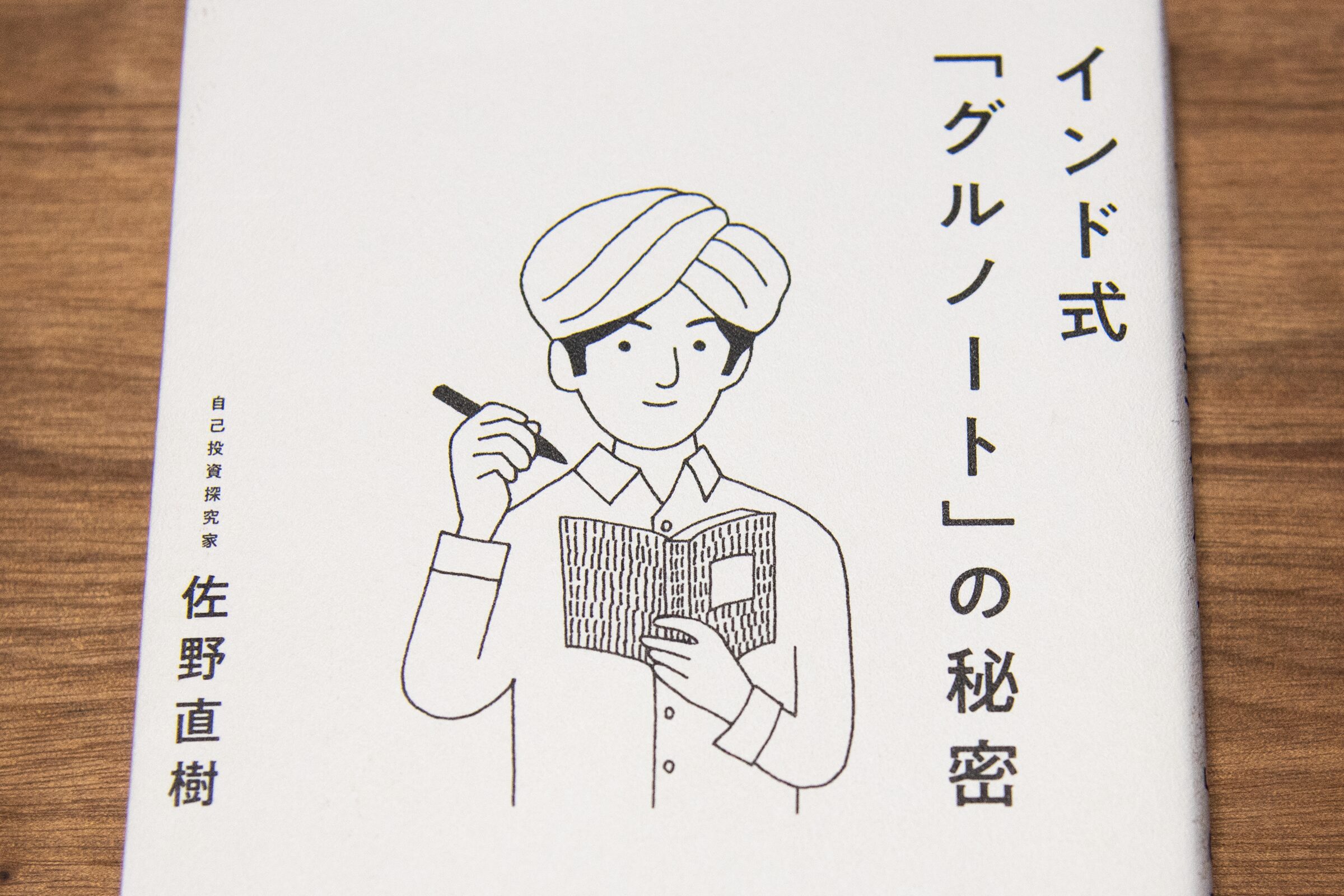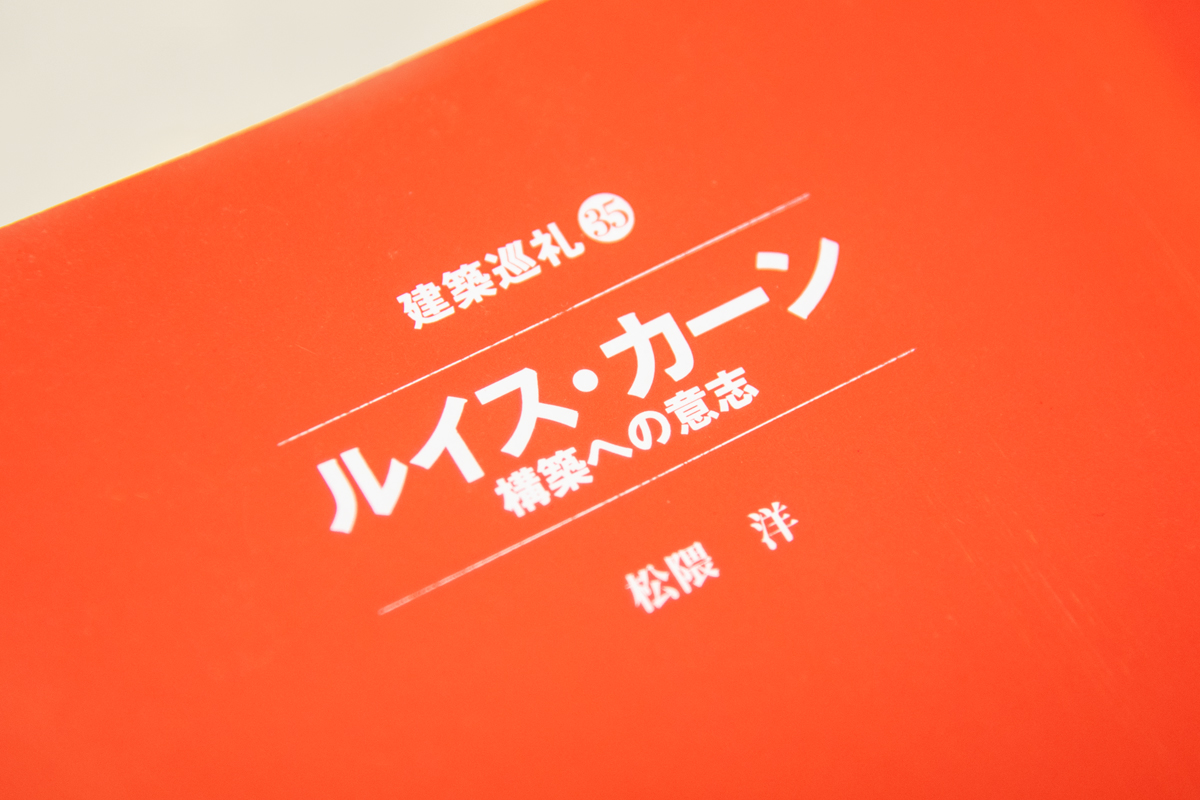「理性」と「愛情」
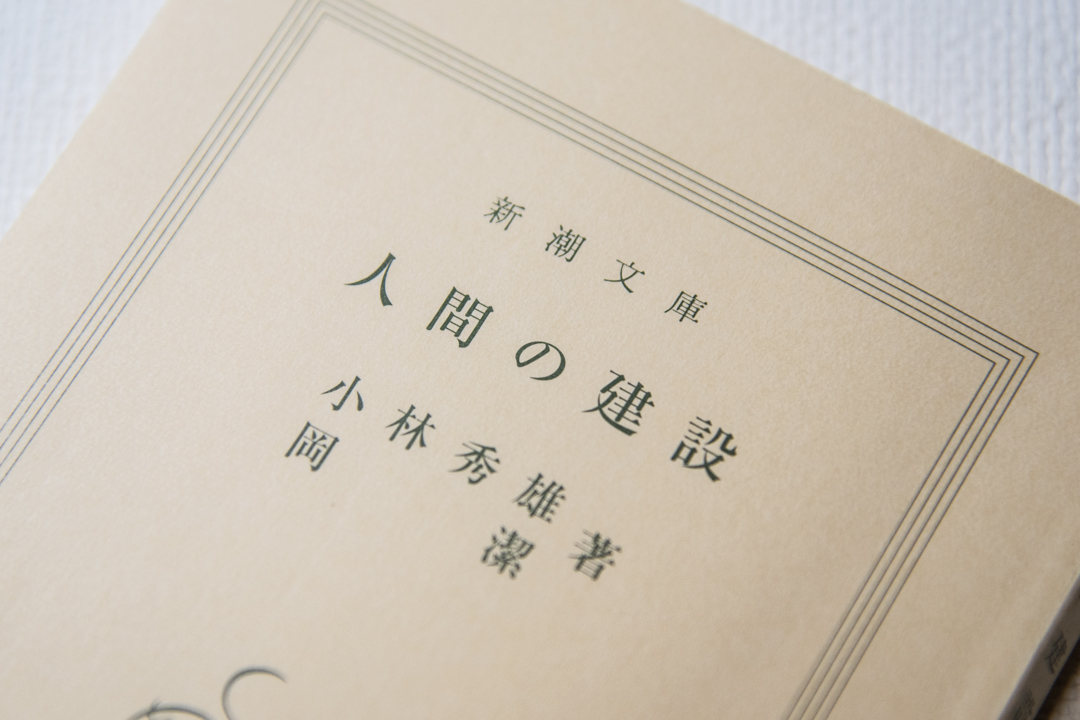
『人間の建設』小林秀雄 / 岡潔 著(新潮文庫)を読んでの所感をまとめる。
古民家の捉え方にもつながる、本質的な物へのアプローチが二人の会話から垣間見える。
『人間の建設』(1965)は、数学者・岡潔と文芸評論家・小林秀雄の対談をまとめた書物で、人間の知性・感情・教育・文化といった根源的なテーマを、自由な語らいの中で掘り下げた知的な記録である。
構成と特徴
本書は明確な主題を設けず、酒や芸術、教育、科学、哲学などを縦横に語る「知的な雑談」とされる。
しかしその中には、二人の学問観や人間理解が深く流れており、形式ばらない思索の交差が魅力となっている。
主な内容
・人間の本質についての対話
小林は「人間が創った文化が、やがて自らを規定していく」と述べ、文化と人間の相互作用を指摘する。
岡は、現代教育が「子どもに考える力を与えず、知識を詰め込むだけになっている」と批判し、感情と直観を重んじる教育を訴える。
・科学と感情の関係
岡は、論理や科学的思考だけでは人間を理解できないと考え、「情(感情)」を人間の中心に据える姿勢を示す。
小林もまた、理性を絶対視せず、芸術や文学が直観を通して真理に到達する道を重視する点で共鳴している。
・現代文明への批評
二人は、合理主義的な科学文明に偏った現代社会を危惧し、「無明(むみょう)」という仏教的な概念をもとに、知のあり方や人間らしさの回復を模索している。
意義
『人間の建設』の「建設」とは、知識や技術を積み重ねることではなく、「考える力」や「感情の深さ」を回復し、人間としての全体性を取り戻す営みを指している。本書は今日でも、「思索とは何か」「人間らしく生きるとは何か」を考えさせる名著として読み継がれている。
以下、引用を用いながら内容のあらましをおさらいする。
学問をたのしむ心
小林 (中略)ところが学校というものは、むずかしいことが面白いという教育をしないのですな。
(中略)
岡 (中略)学問だけではなく、人のふむ道、真善美、もう一つ宗教の妙、どれについても言えることです。
むずかしいことを面白いという感覚の再考。
無明ということ
岡 人は自己中心に知情意し、感覚し、行為する。その自己中心的な広い意味の行為をしようとする本能を無明とという。
(中略)人は無明を押さえさえすれば、やっていることが面白くなってくると言うことができるのです。
小林 (中略)物というものは、人をくたびれさせるはずがない。
岡 そうなんですよ。芸術はくたびれをなおすもので、くたびれさせるものではないのです。
(中略)
岡 ほしいままのものが取れさえすれば、自然は何を見ても美しいのじゃないか。自然をありのままにかきさえすればいいのだ、そのためには、心のほしいままをとってからでなければかけないのだ、そういうふうになっているらしい。
ありのままの重要性と再評価。
国を象徴する酒
岡 物を生かすということを忘れて、自分がつくり出そうというほうだけをやりだしたのですね。 よい批評家であるためには、詩人でなければならないというふうなことは言えますか。
小林 そうだと思います。
岡 本質は直感と情熱でしょう。
この後に両氏とも「勘」が本質、岡氏は「勘は知力」と言及。
数学も個性を失う
小林 抽象的な数学の中で抽象的ということは、どういうことかわからないのですね。
岡 それは内容がなくなって、単なる観念になるということなのです。(中略)内容のある抽象的な観念は、抽象的と感じない。 (中略)つまり、対象の内容が超自然界の実在であるあいだはよいのです。それを越えますと内容が空疎になります。中身のない観念になるのですね。それを抽象的と感じるのです。
魂のある観念と空虚の観念。
科学的知性の限界
岡 文章を書くことなしには、思索を進めることはできません。書くから自分にもわかる。自分にさえわかればよいということで書きますが、やはり文章を書いているわけです。言葉で言いあらわすことなしには、人は長く思索できないのではないかと思います。
岡 数学は知性の世界だけに存在しえないということが、四千年以上も数学をしてきて、人ははじめてわかったのです。 (中略)何を入れなければ成り立たぬかというと、感情を入れなければ成り立たぬ。
岡 人というものはまったくわからぬ存在だと思いますが、ともかく知性や意志は、感情を説得する力がない。ところが、人間というものは感情が納得しなければ、ほんとうには納得しないという存在らしいのです。
小林 いまあなたの言っていらっしゃる感情という言葉は、普通でいう感情とは違いますね。
岡 だいぶん広いです。心というようなものです。知でなく意ではない。
書いたりしゃべったりする中での感情(直感)は本質的なものという合意
人間と人生への無知
小林 ベルグソンの、時間についての考えの根底はあなたのおっしゃる感情にあるのです。
岡 私もそう思います。時間というものは、強いてそれが何であるかといえば、情緒の一種だというのが一番近いと思います。
時間は感情によって、長くも短くもなる。
破壊だけの自然科学
(省略)
アインシュタインという人間
小林 ベルグソンは若いころにこういうことを言っています。問題を出すということが一番大事なことだ。うまく出す。問題をうまく出せば即ちそれが答えだと。この考え方はたいへんおもしろいと思いましたね。いま文化の問題でも、何の問題でもいいが、物を考えている人がうまく問題を出そうとしませんね。答えばかり出そうとあせっている。
岡 問題を出さないで答えだけを出そうというのは不可能ですね。
良い問題を提起できた時点で答えのようなもの。
美的感動について
小林 私はゴッホのことを書いたことがありますが、ゴッホを書いた動機というものは、複製なんですよ。(中略)複製されると、ぼんやりしていて落ち着いてくるのです。複製のほうが作品として出来がいいのですよ。(中略)絵を見るコンディションというものがありますよ。千載一遇の好機に、頭痛でもしていたら、それっきりです。
結局良し悪しを見極めるのも個人の直感ということになる。
人間の生きかた
(省略)
無明の達人
(省略)
「一」という観念
岡 私がいま立ちあがりますね。そうすると全身四百幾らの筋肉がとっさに統一的に働くのです。そういうのが一というものです。一つのまとまった全体というような意味になりますね。
(中略)
情操が文化というものを支えているのではないか。
(中略)
愛と信頼と向上する意志、大体その三つが人の中心になると思うのです。それが人間の骨格を作るのですが、生まれて、自分の中心を作ろうという時期に、家庭にそういう雰囲気が欠けていたら、恐るべき結果になるだろうと言って、おどかしているのです。
(中略)
世界の始まりというのは、赤ん坊が母親に抱かれている、親子の情はわかるが、自他の別は感じていない。時間という観念はまだその人の心にできていない。(中略)ーそういう状態ではないかと思う。そののち人の心の中には時というものが生まれ、自他の別ができていき、森羅万象ができていく。それが一個の世界ができあがることだと思います。そうすると、のどかというものは、これが平和の内容だろうと思いますが、自他の別なく、時間の観念がない状態でしょう。それは何かというと、情緒なのです。だから時間、空間が最初にあるというキリスト教などの説明の仕方ではわかりませんが、情緒が最初に育つのです。自他の別もないのに、親子の情というものがあり得る。それが情緒の理想なんです。矛盾でなく、初めにちゃんとあるのです。そういうのを情緒と言っている。私の世界観は、つまり最初に情緒ができるということです。
個体の発生に伴う情緒の発生。
数学と詩の相似
(省略)
はじめに言葉
小林 (中略)人間に可能でしょうかなどという問題は切り捨てればよいのです。(中略)
岡 わかるということはわからないなと思うことだと思いますね。
(中略)
自分の肉体というものは人類全体の肉体であるべきである。理論ではなく、感情的にそう思えるようになるということが大事で、それが最もできる民族としては日本人だと思います。
(中略)
言葉なんです。思索は言葉なんです。言語中枢なしに思索ということはできないでしょう。
(中略)
人は記述された全部をきくのではなく、そこにあらわれている心の動きを見るのだから、わからん字が混っていてもわかると思います。
言語を通して思索をし、書かれた言語に心の動きも見て取れる。そこにわかるわからない、可能不可能という選択ではない、すべてを行き交う思索が言語化の上に繰り広げられる。
近代数学と情緒
岡 知や意によって人の情を強制できない、これが民主主義の根本の思想だと思います(中略) 情が納得して、なるほどそうだとその人自身が動き出さなければ、前頭葉も働かない。(中略)仏教で、本当の記憶は頭の記憶などよりはるかに大きく外へ広がっているといっていますが、そういうことだと思います。
記憶の本質。
記憶がよみがえる
小林 記憶がやるんです。記憶が幼時のなつかしさに連れていくのです。言葉が発生する原始状態は、誰の心のなかにも、どんな文明人の精神のなかにも持続している。
(中略)
記憶というのは精神の異名なのです。
(中略)
そうすると脳というものは、たとえばオーケストラのタクトみたいなものだということがわかってくるのです。 記憶というオーケストラは鳴っているんですが、タクトは細胞が振るのです。脳がつかさどるものはただ運動です。
(中略)
そうすると記憶と脳との関係は、パラレルではなくなるのです。
記憶と感情(勘)は密接に結びついていて、言語と常に寄り添っている。
批評の極意
(省略)
素読教育の必要
小林 「論語」はまず何を措いても、「万葉」の歌と同じように意味を孕んだ「すがた」なのです。古典はみんな動かせない「すがた」です。その「すがた」に親しませるという大事なことを素読教育が果たしたと考えれば良い。
(中略)
国語伝統というものは一つの「すがた」だということは、文学者には常識です。この常識の内容は愛情なのです。(中略)愛情には理性が持てるが、理性には愛情は行使できない。
岡 理性というのは、対立的、機械的に働かすことしかできませんし、知っているものから順々に知らぬものに及ぶという働き方しかできません。本当の心が理性を道具として使えば、正しい使い方だと思います。われわれの目で見ては、自他の対立が順々にしかわからない。ところが知らないものを知るには、飛躍的にしかわからない。ですから知るためには捨てよというのはまことに正しい言い方です。理性は捨てることを肯(がえん)じない。理性はまったく純粋な意味で知らないものを知ることはできない。つまり理性のなかを泳いでいる魚は、自分が泳いでいるということがわからない。
小林 お説の通りだと思います。
少し次元が違うけれども、この「理性」と「愛情」の話は、「文明」と「文化」の違いと似て非なる比較に思えてくる。
それは現代の新建材住宅と古民家の違いともシンクロする話ではないでしょうか。
以上、本当に一部分の抜粋で、自分のメモとして紹介させていただきましたが、とても本質的で大事なことを双方の会話から垣間見られる貴重な良著です。
ご興味ございましたらぜひお買い求めください。
ではまた。