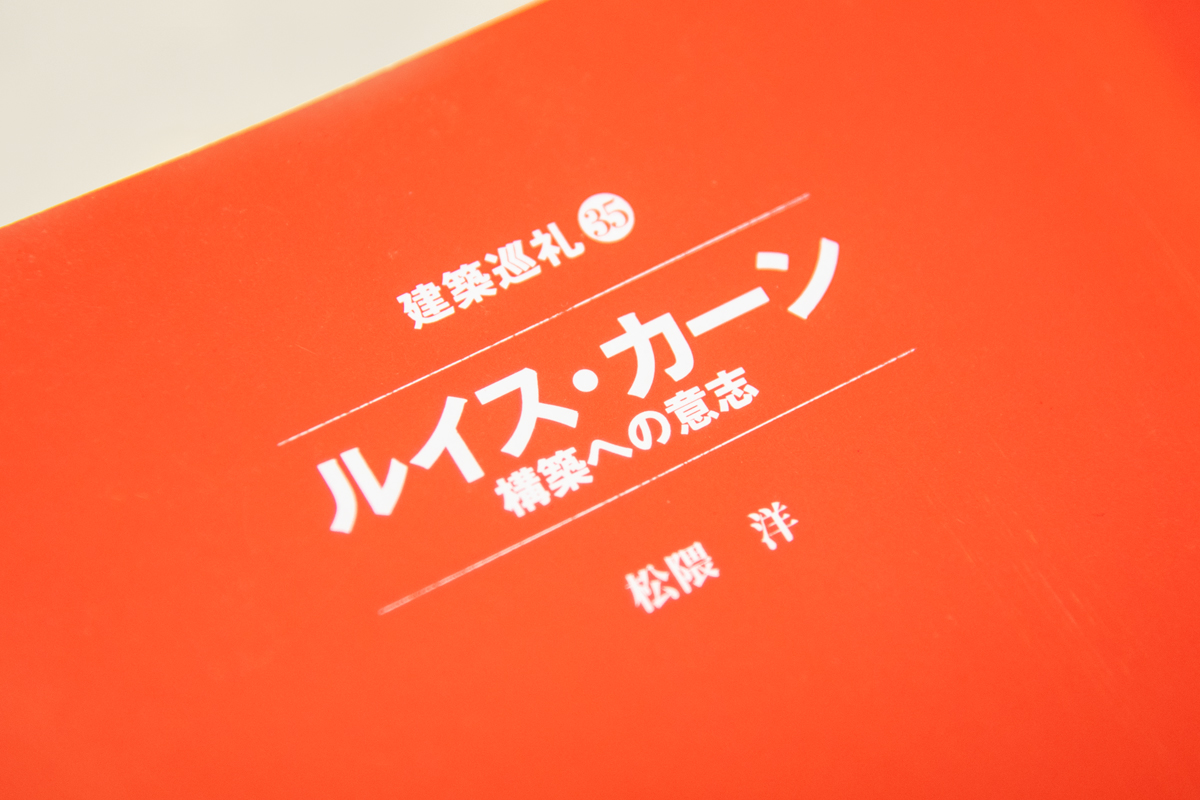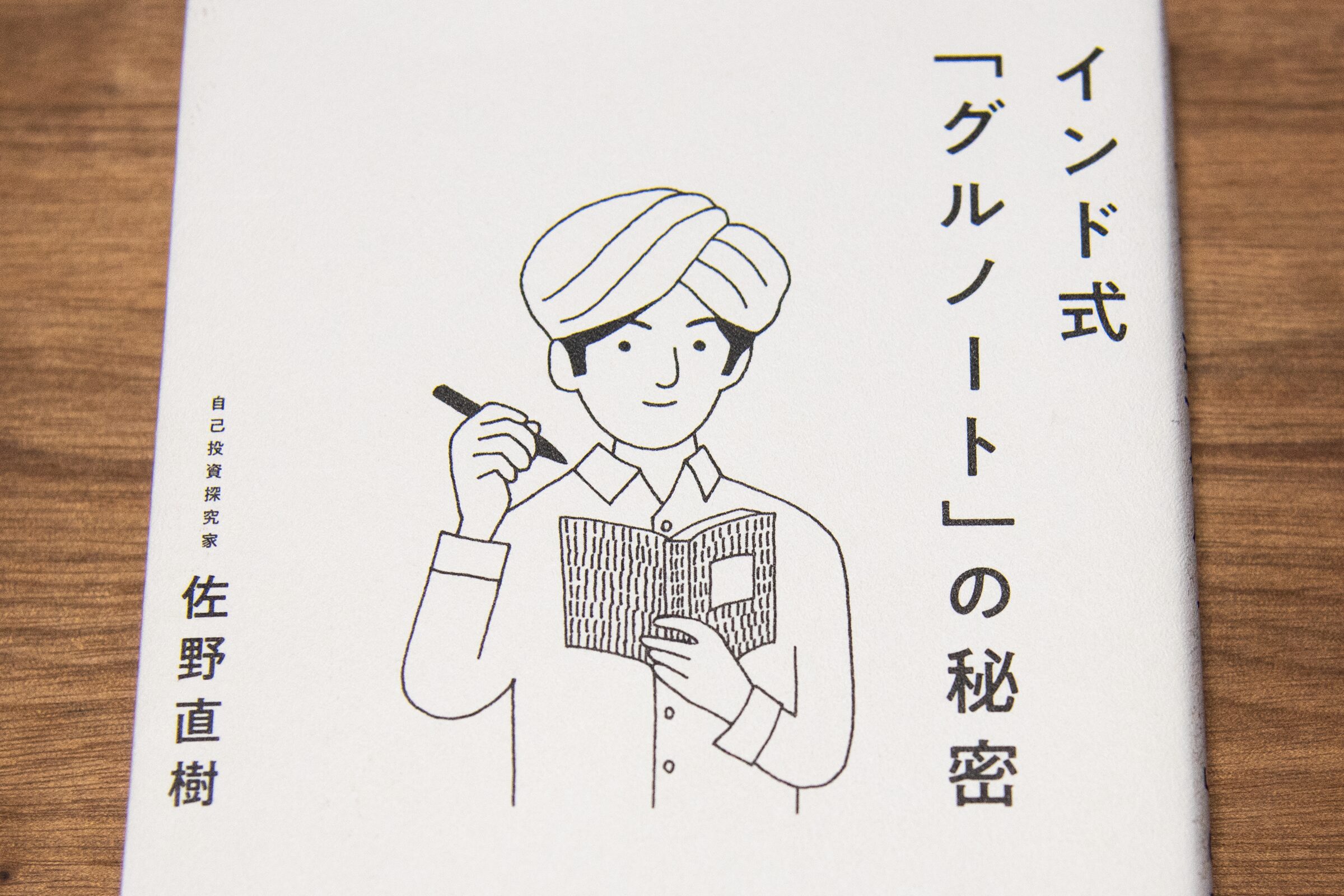建築意匠講義

本質的な建築意匠を考える上で、再度『建築意匠講義』の内容を忘備録として再確認。
毎度のごとく、古民家との関わりから考えていきます。
目次
1. 空間について
2. 部屋について
3. 部屋の集合について
4. 窓について
5. 続・窓について
6. 入口について
7. 場所について
8. 表象について
9. モティフについて
10. 意匠について
11. 分解について
12. 秩序について
1. 空間について
建築するとは、人間のために、空間を秩序づける、ということ:建築が人に対してもつ、重大な責任がある
「秩序づける」という行為に対して、真剣に取り組む姿勢が希薄になりつつある中で、しっかり腰を据えて向き合いたい。
建築シェルター起源論は正しくない
→ 人類は言葉をしゃべりはじめると同時に建物をつくった
→ 『建築は、大いなる超越に対する高遠な試みであって、最高の宗教的行為である』by ルイス・カーン
哲学と通底する領域であり、時折宗教家に見える建築家がいるのもそのためかもしれない。木陰に子どもたちを集めて話し始めるとき、そこは教室となる。
建築は、その関わり方が、より直接的で、そしてより全体的である点で特別:建築物は常に「雰囲気」の中に浸っている
場を作る、街をつくる、気をつくる。
空間は、私自身を中心にして四方に広がっている
→ 空間とは、原初の宗教体験である
→ 中心を固定すること、囲いを確定すること
→ 囲いは、家族、あるいはすべての共同体のの基礎
境界を造り出すとともに、その内外の関係性(あり方)をつくりだす。
2. 部屋について
中心を確定すること
→ 部屋の中の部屋:空間の限定が外に向かって進むだけでなく、内に向かって進む場合もある
入れ子のシステムが、古来建築の中で作られてきた。外との関係(距離)が、機能や構造などの要素と絡めて造られていく。
輪郭を限定すること
→ 囲いは、切るだけでなく、同時に、つなぐものでもある
→ 空間の膨張:内側から外側へ → 建築を生みだす → 特定の方向性を持つ
日本で言う縁側のような中間領域は、様々な風土の中で、様々なレベルで散見される。
初源の小屋:必然的に単純で力強い形態、幾何学的で鋭い輪郭
→ ビギニングス:「デザイン」と「フォーム」by カーン
自然の中にも力強い幾何学が多く存在するように、生命の起源と幾何学は切っても切れない関係なのかもしれない。
3. 部屋の集合について
「建築とは、部屋の社会のことだ。」 by カーン
→ 建築の空間は中心の移動、変容を可能とするものでなければならない
→ 「美とはすべての部分の調和である」
美しい調和を実現するために、秩序が必要なのである。
空間の本質:空間は単なる容器ではなく、内容に形を与えるもの、内容を確かなものとすること
→ 中心が多数あり、移動するような部屋の共同体
本質を実現するために、力強い幾何学が必要になってくる。
建築のデザインの類型
→ 周囲を確定するやり方
→ 内部を囲うやり方
→ 垂直と巡回の運動性:建築の重心は常に上を指向している
→ 線型平面
→ 多中心空間(グリッド):初源的空間
上記の類型から、調和を生み出す。
建築空間とは、私の身体の延長であり、生きた経験として存在するものである
自然(幾何学)に、人類も内包されている。
4. 窓について
光は、部屋をつくりだす、基本的な要素
→ 物体に射してくる光
→ コルビジェ、カーン、ル・トロネ(ロマネスク)、ウィンドウ・シート、ウィンドウ・ルーム
→ 空間を満たす光
→ ライト、ミース、ゴシック、ベイ・ウィンドウ
→ 「照らす光」と「満たす光」は連続的であり、かつ共存し得るもの
光は空間を演出する自然である。
5. 続・窓について
空間が多数の薄い壁で囲まれている場合
→ 建築空間における光は、物の見方にも大きな方向づけを与える
光のレイヤーが部屋の性格を決定する。
空間を何重にも囲み包んでいく面の重なり
→ 「屋根は傘」そして「壁は家具」
大きな傘と家具で建築はつくられる。
“What a slice of sun do you have?”
→ 「窓は、単に窓ではない。様々なものが窓になり得る。窓は様々なものになり得る。」
→ 分類は、架空・便宜的であり、実際はすべて連続的である
光の反射も、光が生み出す影も窓と連続的に果たす役割がある。
6. 入口について
入口:様々な意味が集中している場所
→ 開かれる時があり、また閉じられる時がある
→ ただ入るだけでなく、そこで待つことのできる所でなければならない
→ 人を招き寄せるものであるとともに、拒絶するものでなければならない
→ 留保のための空間
→ 始まりを最もはっきりと示すもの
開ければ外とつながり、閉じれば絶たれるが、入口の在り方によって、内外の距離が変化する。
基本的特質
→ 内部が何であるかを外に向かって示さねばならない
→ 壁の重層の中で成立している
入口の役割と意味。
7. 場所について
「場所」とは「ルーム」の特質を与えられている地形のこと
目に見えない要素が生み出す領域。
場所とは、共同体の拠り所、支え
それぞれの人が持ち得る魂。
ゲニウス・ロキ
そしてその場所で引き継がれてきた地霊。
自然の形と人間の作る形との対比
→ 「建築は、場所の特性を視覚化する。」
→ 場所の記憶を忘れるな
人間は、目に見える自然と目に見えない自然を可視化させている(本来の建築)。
8. 表象について
建築とは、いかに住んでるかを表すもの
社会との関係において成立する。
表象論:外に示す存在としての建築について考える
その関係性をどう捉えているかの表明。
建築は、自分のためにつくられると同時に、他人に向かっても建てられるもの
周囲との関係性がより強い田舎では、右に習えの建築が多いのもこの意識からか。
建築は芸術的に形成された現実である
→ 人間の共同の価値を表現することこそ建築が最も力を発揮するところ
→ 建築という芸術は、否定ではなく肯定を、悲しみよりは喜びを、不安よりは希望を、闇よりは光を表すのにふさわしい芸術
→ 私ひとりの光、ではなく、私たち共同の光を表す
→ 建築は分裂の中において成立することはできず、常に一致の上にしか成り立たない:デューイの言う「不朽の銘文」
共同体の形成。
9. モティフについて
「囲いモティフ」と「支えモティフ」の対立的統合
→ 形相(qualia)
→ 彫刻:立体
→ 自由に移動できる
→ 建築:空間
→ 定義:人間を囲って成立し、人を包み覆うもの
→ 場所に根を下ろす
→ 大地によって支えられ、自らも支える
→ 三部構成:大地と接する基部、大空に接する頂部、両者の中間部
周囲の関係の中で、同化しながら中間に存在する。
よって風土によって若干の違いが見られる。
10. 意匠について
「囲いモティフ」と「支えモティフ」の争いに一つの一致が見られた時の形態
→ 形態は、変形されることによって、完成とは何であったかが明らかにされる
→ 20世紀建築は、「支えモティフ」と「囲いモティフ」の闘争が、いっそう激しく、いっそう分断された形で行われている
社会の情勢が変化したことにより、建築も変化した。
11. 分解について
様式折衷主義
様式の取捨選択が時代の変遷の過程で交錯する。
建築は選択の連続。
還元主義(革命願望):20世紀に入ってからのデ・スティル、未来派、都市計画、
→ ロシア構成主義:「支えモティフ」と「囲いモティフ」を可能な限り拒否、浮遊性・運動性、政治的側面
→ 有機主義:不定形な力、流動する空間を包み込もうとする「囲覆性」
→ 表現主義的幻想:英雄的で、その失敗の中にもある種の偉大さが存在する
社会の中で、権威を表現する時代。
12. 秩序について
創作行為における否定、あるいは懐疑
→ ニヒリズム:「建築家は、虚無から創造するわけではない。」by レーウ
→ 「建築とは芸術的に形成された、現実性、である。」by ダゴベルト・フライ:否定という姿勢のみから建築を生み出すことはできない(できなかった)
豊かさから生み出されるものであるべき。
秩序:「建築家とは空間を秩序づける人だ。」「空間を秩序づける人は神の模範的仕事を繰り返している。」by エリアーデ
→ 「作業場の実在論」:コルビュジェ、ライト、ミース
造作への責任。
民芸、民家:秩序を判断する力=全ての人に共有されているもの:行うことによってのみ明らかにされる「他力の美」
→ 時代性(建築は「時代」を表現し、「時代の精神」を示す)という考え方の氾濫
→ 情報メディアの問題:「虚構の表象」
社会的な存在であるが故、尚更本質を見失わないでいることが求められる。
秩序:道徳的確信、行動的信念の中においてのみ得られる
→ 建築を作るということは、この生きた世界の中であくまでも生きた現実と関わって秩序を求める態度
よって秩序付けられた生き方ができて本質を知って表現できる必要がある。
建築の本質を顧みる良著です。